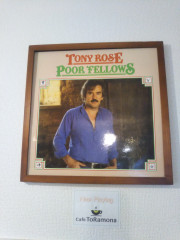Information
最近コレクションできた7インチ・シングルをご紹介します。
Ye Vagabonds『I'm A Rover / Bothy Lads』(River Lea Records, 2021)
Ye Vagabondsはスウィニーズ・メンやプランクシティの真の後継者と云われるアイルランドの若手兄弟デュオ。A面〈I'm A Rover〉はアイルランドやスコットランドでは有名なナイト・ヴィジティング・ソングで、彼らのヴァージョンは幼少の折、母のGraniaから習ったもの。B面の〈Bothy Lads〉はシラ・フィッシャーとアーティー・トレザイスのシンギングをお手本にしたそうです。シラとアーティーはフォークレガシー盤『For Foul Day and Fair』で唄っていましたね。
Neal Casal『Everything Is Moving / Green Moon』(Royal Potato Family, 2021)
ニール・カサールの7インチは生前ニールが残したベーシック・トラックに友人たちが手を加えて完成させリリースされました。〈Everything Is Moving〉は2013年2月ごろブルックリンのスタジオで録ったバンド編成のトラックに、昨年7月Jon Graboffがペダル・スティールとエレクトリック・ギターを、John Gintyがピアノとハモンドを、そしてJeff HillとJena Krausがハーモニー・ヴォーカルをダビングして仕上がりました。また〈Green Moon〉は2016年の夏にヴェンチェラの自宅近くのスタジオで一人でギターやピアノを弾き、コーラスまで唄ったトラックに、昨年10月Jeff HillとGeorge Sluppickがベースとドラムを加えたものです。いつもながらの歌声ですが、どこか悲しげに響きます。
Van Dykes Park『Histories (Old Black Joe) / Souvenir de la Havane』(Corbett vs Dempsey, 2021)
ヴァン・ダイク・パークスの新作はフィラデルフィアで活躍するアーティスト、デイヴィッド・ハート(David Hartt)のインスタレーション作品用にアレンジを依頼されたフォスターの〈オールド・ブラック・ジョー〉。デイヴィッドのインスタレーションThe Histories (Old Black Joe)は2枚のタペストリーと4つのアンティーク・チェア、そしてヴァン・ダイクの〈オールド・ブラック・ジョー〉で構成されていますが、タペストリーを流用したレコード・ジャケットを眺めながら、流麗なオーケストラにスライド・ギターやスティールパン、はたまたミンストレル・ショーをコラージュしたような〈オールド・ブラック・ジョー〉を聴いていると件のインスタレーションを鑑賞した気分になれるかも。B面はヴァン・ダイクが多大な影響を受けたゴットシャルクの〈Souvenir de la Havane〉。ヴァン・ダイクはアッシュ・グローヴのライヴ盤でも彼の作品を取り上げていました。
ご来店の際にリクエストしてください。
カフェトラモナ3月のおすすめです。
上左:Jimbo Mathus & Andrew Bird / These 13(Thirty Tigers, 2021)
ギターのジムボ・マサスとフィドルのアンドリュー・バードが出会ったのは1994年ノース・カロライナのブラック・マウンテン・ミュージック・フェスティヴァルでした。その後アンドリューはジムボのスクィーレル・ナット・ジッパーズに参加し一緒にプレイすることになりますが、「いつかフィドルとギターだけでジンボと一緒にレコードを作りたい」とずっと思っていたとのこと。プロデュースはマイク・ヴァイオラ。スタジオの中央にマイクを1本だけ立て、アナログ・レコーダーで一発録りしたそうです。これらの13曲はすべて2人のオリジナルですが、昔ながらのカントリー、ルーラルなブルース、アパラチアン・ミュージックにホワイト・スピリチュアルとどれもオーセンティックかつアーシーなルーツ感満載のアルバムです。
上右:Neil Young / The Times(Reprise Records, 2021)
昨年ネット上で公開された「Fireside Sessions」シリーズ第6弾の「Porch Episode」をEP化したもの。もともとCDとAmazon musicでリリースされていましたが、今年になってアナログ盤もお目見えしました。コロナ禍のなか大統領選とブラック・ライヴズ・マターで大きく揺れ動くアメリカ合衆国で、〈Alabama〉〈Ohio〉〈Southern Man〉など必然的にメッセージ色の強い選曲になったようです。アルバムのタイトルはディランの〈The Times They Are a-Changin'〉のカヴァーから。かつて〈Campaigner〉でニクソンやブッシュにさえ魂があると唄っていたニールですが、今回はトランプにさえ魂があるとは流石に唄いませんでした。
下左:Josh Okeefe / Bloomin’ Josh Okeefe(Anti-corp, 2020)
英国はダービー出身のSSW、ジョシュ・オキーフのデビュー・アルバム。16歳で学校をドロップアウトし、ロンドンやブライトンを放浪。コーヒー・ハウスやレコーディング・スタジオの床で夜を明かしたこともあるとか。2017年にリリースした EP『Josh Okeefe』が評判となり、2019年夏には ビリー・ブラッグの招待でグラストンベリーに出演したこともあります。録音はディランとジョニー・キャッシュが共演したナッシュヴィルは伝説のコロンビア・スタジオA 。ギターとハーモニカの弾き語りスタイルは初期のディランからジャック・エリオットやガスリーにまで遡れますが、〈Young Sailor〉にはイワン・マッコールからポーグスへと連なる英国フォーク・ムーヴメントの叙情性も窺えます。
下右:Tony Rose / Poor Fellows(Dingle's, 1982)
買い逃していたトニー・ローズの4枚目がコレクションできました。トニー・ローズは4枚のアナログ盤と2枚のCDを残すも2002年に癌で亡くなってしまったイングランドのリヴァイヴァリスト。1978年にニック・ジョーンズやピート&クリス・コーと組んだBandoggsは「円熟期の英国トラッド・フォークが到達した一つの理想郷」と評され、フォークのスーパーグループと云われていました。本作はそのバンドックスの活動を挟んで前作から6年ぶりにリリースされた1982年のソロ・アルバム。トラッド中心に唄ってきたトニーですが、R・トンプスン作〈Down Where the Drunkards Roll〉やP・ベラミーの〈Us Poor Fellows〉など同時代の作家による楽曲をアルバムの半数で取り上げているのが印象的です。極めつけはディランの〈Boots of Spanish Leather〉で、数曲で聴けるベースやシンセが時代を感じさせますが、基本的にはギターとコンサティーナの弾き語り。ベテラン・リヴァイヴァリストによる落ち着いた歌声が味わい深い名盤です。
ご来店の際にリクエストしてください。